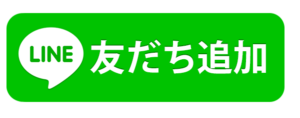児童発達支援管理責任者(児発管)は、障害を持つ児童が適切な支援を受けるために必要で障害児福祉施設における重要な存在です。
この職は、児童の個別支援計画を作成し、提供されるサービスを管理する役割が主な業務になります。
また、児童の家族と行政や他の施設との間での調整役も果たし、児童福祉の中核を成す重要な職といえるでしょう。
ではそんな児童発達支援管理責任者(児発菅)にはどうやってなれるのでしょうか?
児童発達支援管理責任者の業務
先程もお伝えしましたが、児発管の主な業務は、障害を持つ児童のための個別支援計画の作成と管理です。
この計画は、児童一人ひとりのニーズに合わせて作成され、彼らが必要とする様々な支援サービスを統合的に管理します。
また、これらの計画に基づいて、具体的なサービスの提供が行われ、その効果の評価や調整も行います。
さらに、児発管は児童の家族との連携も担当します。
家族への相談や支援の提供はもちろん、必要に応じて他の福祉サービスや行政との連携を行い、児童と家族が必要とするサポートを確実に受けられるよう努めなければなりません。
児童発達支援管理責任者のOJT
2019年に児発管に関する制度が改正され、より専門的な知識と経験が求められるようになりました。
改正により、児発管として働くためには特定の研修を受けるだけでなく、2年以上のOJT(On-the-Job Training)が必要とされるようになりました。
OJTは、現場での実践を通じて、理論と実務の両方のスキルを身につけるための重要なプロセスです。
児発管は、障害児支援施設に最低1名以上配置されることが義務付けられています。
ただし、児童指導員との兼任は認められていないため、児童指導員としての業務と児発管としての業務は分けて行われる必要があります。しかし、施設の管理者との兼任は可能とされています。
OJT期間中には、既に専任の児発管がいる施設においてのみ、2人目の児発管としての配置が認められます。
この場合、児童指導員としての配置も可能ですが、この点については自治体によって見解が異なることがあります。
また例外的に2年間のOJTが6カ月に短縮されることもあります。 こちら関しては今後また詳しく解説します。
児童発達支援管理責任者 OJT | まとめ
児発管の役割は、障害を持つ児童一人ひとりに合わせたサポートを提供し、その生活の質を向上させることにあります。
これにより、児童だけでなく、その家族全体の福祉が向上します。
また、他の福祉サービスや行政との連携を通じて、地域全体の児童福祉のネットワークを強化する役割も担っています。
このように、児発管は障害児支援の分野で中心的な役割を果たし、障害を持つ児童とその家族が適切な支援を受けることができるようにするための重要な存在ですし、今後需要も高まることでしょう。
だからこそ長い期間のOJTが必要だったのですが、児発管が少ないうえに需要が高い職業なので、OJT期間を短くするなどの対応を行政も取るしかないというのが現状の様です。