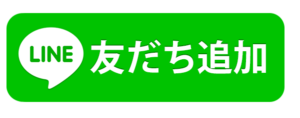生活相談員として活躍するうえで必要な資格は、基本的には社会福祉士や精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格が必要になりますが、基本的に無資格でもなれる可能性はあります。しかし、一つだけ取得しておくべき資格があります。それは普通自動車運転免許(普通自動車第一種運転免許)です。生活相談員の仕事の中には利用者様の送迎業務も含まれる場合もあり、業務の一環で利用者様を乗せてご自宅まで向かうことも含まれます。そのため普通自動車運転免許の取得が必要になるのです。
今日は生活相談員の送迎業務について解説してみたいと思います。
生活相談員が利用者様を送迎するうえで気を付けておくべきこととは?
生活相談員の仕事の中には利用者様の送迎業務も含まれます。職場によっては専門の送迎スタッフがおられる場所もあると思いますが、基本的には生活相談員も送迎業務に携わることがあると思っておく必要もあるかもしれません。
その送迎業務では特に気を付けておくべきことがあります。それは車から乗り降りをする際の転倒や徘徊です。
昨年、大阪府内の通所支援事業所で送迎業務中に利用者が徘徊して死亡するという事件が起きました。
車から施設内まで介助が必要にもかかわらず一人で移動させたことが問題だったという話がニュースでも取り上げられました。
こうした事例は子供だから起きたわけではありません。高齢者であっても考えられる問題でもあります。
高齢者の徘徊は常に年間数例はテレビでも紹介されています。そのため送迎のタイミングで徘徊してしまい行方不明になるということも少なくありません。
送迎業務においてはこうしたところに注意を向け、利用者様を安全に自宅から施設までお連れするというリスクを考えて対応していく必要があります。
また、車のステップというものは比較的高く、患者様によっては結構高さが高いと感じる方も少なくありません。
そのため昇段時も降段時も気を抜いてはいけません。いつ膝折れを起こす可能性があるかわかりませんので注意しておきましょう。
送迎業務はただ利用者様を自宅から施設までお連れする仕事ではありません。
利用者様の命を預かり、安全安心にお連れする必要があるのです。だからこそ注意して運転する必要がありますね。